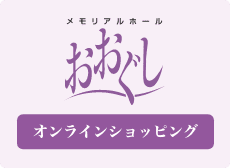ご葬儀の流れ・基礎知識
病院や施設等で亡くなった場合、まず何をすればいいんだろう・・誰しもそう考えると思います。ここでは、ご臨終から葬儀式が終わるまでの一般的な流れをご説明します。
※ご自宅で亡くなった場合は、まずかかりつけの医師にご連絡を!
※ご自宅で亡くなった場合は、まずかかりつけの医師にご連絡を!
| ご遺族のお仕事 | 葬儀社のお仕事 | |
|
ご臨終 ご移送 ご安置 |
●家族や葬儀社に連絡 ●医師から診断書を受け取る ●ご安置場所の決定 ●ご安置の後、お線香を上げ枕飯・枕団子を供える |
●搬送車で病院・施設等にお迎え ●ご遺体を自宅等に移送してご安置 ※当社安置所にて預かる事も可能です ●宗派別に枕飾りを整える ●ご希望により枕飯・団子の用意 |
|
打ち合わせ 連絡確認 |
●日程にもよりますが、内容のほぼ90%以上を決定 ●日時、場所を関係各位に連絡しながら会葬予定人数を確認 ●死亡届(死亡診断書)の記入 |
●詳細打ち合わせ→見積書作成→ご遺族確認及び承認→手配開始 ●連絡、確認などの状況を受け手 配を整える ●死亡診断書をお預かりして役所にて手続き |
|
ご納棺 ご移送 |
●近親の皆様が集い、故人に旅支度を着け納棺する(湯灌) ●柩に故人に持たせたい物など、一緒にお納 めする |
●ご希望により納棺師の手配 ●納棺のお手伝いとご案内 ●通夜式場に故人様をご移送する |
|
お通夜 |
●生花など供物の序列や席次を決め開式15分前に席に着く ●代表の挨拶をする方・通夜振る舞いでの献杯をされる方・焼香時に立礼される方の選出 ●受付などの係員は1時間前に所定の配置に着く ●ご親戚の皆様とともにご接待(通夜振る舞い)の席に着く ●告別式の確認 |
●設営装飾の完了、最終確認 ●導師と打ち合わせをし指示をいただく ●開式前案内、誘導 ●弔辞・弔電の確認 ●式中案内、誘導、司会進行 ●告別式の確認(返礼品・料理等の数の変更など) |
|
葬儀 告別 ご出棺 |
●生花など供物の序列や席次を確認し開式15分前に席に着く ●受付などの係員は1時間前に所定の配置につく ●故人様と最後のお別れ(お花や持たせたい物を納める) ●ご出棺 |
●設営装飾の確認 ●火葬場同行人数の確認 ●弔事・弔電の確認 ●導師と打ち合わせをし指示をいただく ●開式前案内、誘導 ●式中案内、誘導、司会進行 ●お別れのお支度 ●ご出棺お手伝い・誘導 |
|
火葬(茶毘) |
●火葬場の炉前で最後の故人様とのお別れ ●火葬中(1時間半〜2時間)休憩室で収骨を待つ ●皆様で遺骨をお骨壷に納める ●埋葬許可証を遺骨とともに受け取る |
●火葬場同行案内、誘導 ●火葬許可証提出 ●お部屋(お席)に案内 ●ご収骨の案内、誘導、説明 ●諸費用精算(代行を含む ●車両への乗車案内、誘導 ●繰り上げ法要などの用意 |
|
繰り上げ法要 精進落とし |
●繰り上げ初七日法要など精進落としと呼ばれる席で、臨席の皆様の労をねぎらい、故人様を偲ぶ |
●法要の案内、誘導、進行 ●精進落しの席への案内、誘導 ●お帰りの方の車両などの手配とお見送り |
|
位牌 遺骨 遺影の安置 |
●ご安置場所を決定(約1畳分) ●体力と時間が許せば近隣へのご挨拶をすませる ●ゆっくり休む |
●火葬場で過ごしている間に鍵をお預りして安置棚や供花等を移動、又は収骨後同行して移動、設置 |
◆ お焼香の基礎知識
お焼香のしかた
(1)数珠は左手に持ち、房(ふさ)の部分が下に来るようにします。焼香台に進む前に、遺族、住職に一礼してから焼香台の方に静かに進みます。(※数珠は、仏教徒以外は持ちません。原則として数珠を持つときは左手に持ちます。)
(2)焼香台の3〜4歩手前で止まり、遺影と仮位牌を見つめてから、改めて台の一歩手前まで進みます。
ここで一度合唱をします。合唱の際は、数珠を持った左手に、空いている右手を添えるようにして(または数珠を両手にかけて・・・宗派によって異なります)手を合わせます。
(3)焼香台の右前にある抹香を、右手の親指・人差し指・中指の3本指でつまみ、頭を垂れるようにしたまま目を閉じながら額のあたりの高さまで捧げます。
(4)額までかかげた手をおろしながら、抹香を静かに左側の香炉の中に落とします。これを1〜3回繰り返します。(焼香の回数は宗派によって異なります。)
人数が多く、混雑してる場合などは、1回だけ丁寧にたけば良いでしょう。
(5)焼香が済んだら、もう一度合唱をします。
次に、遺影の方を向いたまま下がり、住職・遺族に一礼し、向きを変えて自分の席に戻ります。
(2)焼香台の3〜4歩手前で止まり、遺影と仮位牌を見つめてから、改めて台の一歩手前まで進みます。
ここで一度合唱をします。合唱の際は、数珠を持った左手に、空いている右手を添えるようにして(または数珠を両手にかけて・・・宗派によって異なります)手を合わせます。
(3)焼香台の右前にある抹香を、右手の親指・人差し指・中指の3本指でつまみ、頭を垂れるようにしたまま目を閉じながら額のあたりの高さまで捧げます。
(4)額までかかげた手をおろしながら、抹香を静かに左側の香炉の中に落とします。これを1〜3回繰り返します。(焼香の回数は宗派によって異なります。)
人数が多く、混雑してる場合などは、1回だけ丁寧にたけば良いでしょう。
(5)焼香が済んだら、もう一度合唱をします。
次に、遺影の方を向いたまま下がり、住職・遺族に一礼し、向きを変えて自分の席に戻ります。
Q.諸事情があり、故人を自宅に安置できない時はどうしたらいいの?
A.ご安心ください。お迎えの依頼をする時に、自宅には連れて帰れない旨をお話し下されば、当社安置所にて、故人様をお預かりいたします。安置所につきましては、午前9時より午後5時まで開放しておりますので、時間内はいつでもお焼香出来ます。
Q.急な事で、決まったお寺は無いけど、お坊さんを呼んで葬儀が出来るの?
A.ご安心ください。希望をお伺いした上で、当社より寺院へ連絡をし、葬儀の依頼を代行いたします。
依頼した寺院の檀家になるか、ならないか。檀家にならない場合、戒名をつけてもらうか俗名のままでお勤めしてもらうのか。等々をお伺いします。
Q.組内に手伝いを頼む事が出来そうもないけど大丈夫?
A.ご安心ください。当社スタッフが、受付・引換・火葬場接待等、お組合様に代わってすべて引き受けます。
Q.お通夜の夜、遺族はホールへ泊まらなくちゃいけないの?
A.ご安心ください。当ホールにて故人様をお預かりいたしますので、ご遺族様はお帰りになっても大丈夫です。これまでの看病疲れや、慣れない事への精神的負担など、体調を崩しやすい時なので無理をしないことをお勧めします。
Q.お墓がまだないんだけど、お骨はどうしたらいいの?
A.ご安心ください。お墓建立の予定が決まっている方は、葬儀終了後当社で用意した「後飾り壇」へ納骨が終了するまでご安置しておけます。まだしばらくは建立予定がない方は、当社に、お骨を収めることの出来るお仏壇もございますのでご相談ください。
Q.感染症対策は大丈夫なの?
A.ご安心ください。入口の記帳所に3か所、受付テーブル、通路等に除菌スプレーを設置しており、体温計測器をハンディタイプとスタンドタイプの2種類ご用意しております。また、自由焼香用の焼香台を設けておりますので開式前、参列者が少ない時間帯にお焼香をすることが出来ます。式場内は、ソーシャルディスタンスを確保するべく椅子を1脚づつ空けて着座して頂いております。使用後の椅子やテーブルボールペン等は、速やかに除菌対策をしております。以上のことを踏まえてスタッフ一同万全の注意を払って対処しております。もし、当ホールへお越し頂いてから体調に異常が生じましたら遠慮なくお申し付けください。